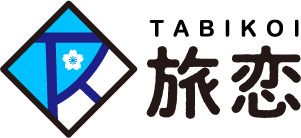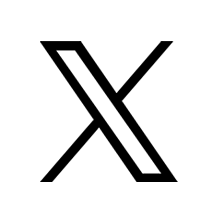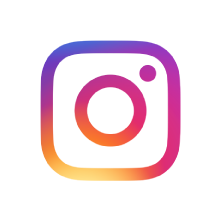「祇園 花街芸術資料館」をご紹介します。その前に花街とその歴史についてです。
京都には五花街があります。祇園甲部、祇園東、宮川町、先斗町、上七軒です。およその場所ですが、祇園甲部は四条通から花見小路を南に下り建仁寺に至る地域と、北側に位置する花見小路西側の一帯を中心とした地域、祇園東は四条花見小路から北へ新橋あたりまでの地域、宮川町は南座の一筋南の団栗通から始まる宮川筋を中心に柿町通あたりまでの地域、先斗町は鴨川西の先斗町通を中心に三条通から四条通の地域、上七軒は北野天満宮の東から今出川通まで斜めに走る上七軒通を中心とした、北野天満宮に隣接した地域です。上七軒だけが離れた場所にあります。
それぞれの歴史ですが、祇園甲部は寛永年間(1620~1646)あたりから、ほど近い八坂神社の門前茶屋街として栄えだしました。江戸幕府三代将軍徳川家光の時代です。祇園東は、明治14年(1881)に当時の京都府知事の命により祇園町から分割独立しました。宮川町は慶長年間(1596~1615)に出雲の阿国が、四条河原で歌舞伎踊り小屋を始めます。あたりが歓楽街へと発展する中、茶屋街として発展しました。先斗町は正徳2年(1712)頃から高瀬川開通により集積所となり商家、旅籠が多く建ち並び、それに伴って花街ができたのが始まりですが、正式に芸妓取り扱いの許可が下りたのは文化10年(1813)とされています。上七軒は室町時代中期に北野天満宮再建に使った建材の残りで、7軒の茶屋ができたのが始まりで、その後天正15年(1587)に北野大茶会を催した豊臣秀吉に許され茶屋街になったとされています。
各花街は京都以外では見当たらない古い歴史と伝統があります。大事なことは時代時代によって支えてきた人は様々ですが、このおもてなし文化という芸術が現代社会にまで脈々と引き継がれてきたということだと思います。しかし京都人の私でも花街は敷居がとても高く、中の様子はなかなかうかがい知れません。
ところが令和6年(2024)5月15日に、祇園甲部の歌舞練場に隣接した木造二階建ての八坂倶楽部内に「祇園 花街芸術資料館」が開館しました。建物は大正天皇即位の祝宴会場として建設され、祇園甲部歌舞練場とともに国の登録有形文化財になっています。
入って正面の間には「都をどり」で使われる着物と道具が展示してあり、次の部屋には様々な花簪(はなかんざし)や舞妓さんの履物「おこぼ」、舞扇、実際に使う化粧道具や持ち物などが多数目の前に展示してあります。ただし手に取ることはできません。
 左上から時計回りに細かい手仕事の花簪、舞妓さんが履いている「おこぼ」、化粧道具などの小物、舞扇
左上から時計回りに細かい手仕事の花簪、舞妓さんが履いている「おこぼ」、化粧道具などの小物、舞扇
向かいの部屋には人間国宝である京舞井上流五世井上八千代氏の映像が流れています。ちなみに舞は明治5年(1872)の第一回「都をどり」から井上流で、祇園甲部はすべて井上流です。奥の庭に面した広間には三味線や鼓の展示、興味深く解説されたパネルがずらりと並んでいます。
庭を望む座敷には座布団が並べてあり、のんびり過ごせます。また縁側から外に出て池泉庭園を散策できます。夜はライトアップされた庭と「つなぎ団子」の紋章が入った赤提灯の灯かりの情景が幻想的です。
二階に上がると華麗な手描き友禅の着物や西陣織の帯、祇園でもめったに見られない正装の黒紋付などの美術品が所狭しと展示してあります。隣の舞台では、別料金ですが芸妓さん・舞妓さんの京舞が披露されます。隣接した歌舞練場本館も見学できて、時期によっては花道と舞台にも立つことができます。
 祇園甲部にちなんだ小物や食品などセレクトショップのようで、割烹でよく見るうちわも販売されている
祇園甲部にちなんだ小物や食品などセレクトショップのようで、割烹でよく見るうちわも販売されている
ミュージアムショップには祇園甲部にちなんだお土産を集めてあります。ブロマイドのような芸妓さん舞妓さんのポストカードなどが面白いです。
併設したアートカフェでは地酒や日本産ウィスキーなどを、過去の「都をどり」ポスター原画の展示と庭を眺めながらいただけます。
〒605-0074京都府京都市東山区祇園町南側570-2 八坂倶楽部
開館時間:11:00~19:00(入館は18:15まで)
休刊日:3月中旬~5月上旬・年末年始・その他不定休
料金:一般1500円 大学生以下700円 未就学児無料 修学旅行の小中学生に限り400円
舞妓さん芸妓さんによる京舞披露鑑賞 1600円 修学旅行の小中学生に限り700円
1回目13:30〜 2回目14:20〜 3回目15:00〜 4回目16:00〜 5回目16:30〜
舞妓さん芸妓さんと記念撮影 1組当たり2000円
1回目13:50~ 2回目15:20~