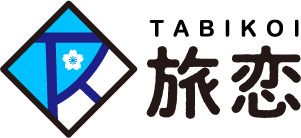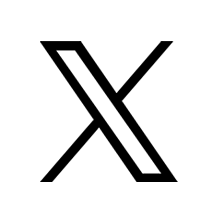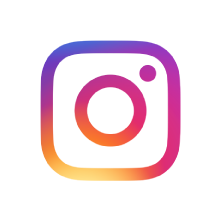京都の北西部の高台に広がる鷹峯は、かつて本阿弥光悦が光悦村と呼ばれる芸術集落を形成し、京都の文化・芸術の一大拠点でした。そこからさらに1㎞あまり天神川に沿って山道を行くと、仏谷と呼ばれる北山杉に囲まれた地区に、京小鍛冶 祥啓(きょうこかじ しょうけい)という屋号の鍛冶師の工房があります。
 車一台通れる街道から少し高台に入った作業場、
車一台通れる街道から少し高台に入った作業場、
水道は山水で陶工や写真家の工房も隣接してある
ひとり、その工房で刃物や鉄製品の制作をされている、船木祥啓(ふなきよしひろ)さんにお話を伺いました。船木さんは横浜出身で、実家が鍛冶師でそれを継がれたのでもありません。むしろお母親は、鍛冶師になることに大反対されました。母方の祖父は鍛冶師で、すでに斜陽産業になっていたからのようです。しかしお父様が、三菱マテリアルに努められていたので、本棚に冶金学や刃物の書籍が多くあったことと、子供のころから農器具を研いでいる近所の農家の方に研ぎ方を教えてもらうなどして自然に刃物が好きになっていったそうです。
高校卒業後、自転車で産地を巡り、新潟三条で知り合った鍛冶師の「刃物を作るには使われ方を知らなければダメだ」との助言に従って料理の世界に入ります。辻調理師専門学校を卒業後、京都の京料理店で2年間休む間もなくみっちり修業をしたのち、本来の目的である鍛冶師の道に進みます。
よく通っていたピザ屋のご主人に紹介された京都の刃物会社で、10年間刃物作りの修業と営業をこなして2005年に独立、この鷹峯の山奥に工房を構えられました。今まで無駄なく来られたのは、船木さんの父方の先祖が平安時代後期に奥州藤原家とつながり、室町時代には土崎湊の警護をし、その後代官・軍船奉行などを仰せつかっていたこと、母方の祖父が幻の刀と呼ばれる奥州舞草刀の探求を願っていたこと。船木さんはそのDNAを強く引き継いでいるようです。工房内の作業場は、1ⅿ四方を1m近く掘り込んで目の前で工作ができるようになっています。ここで船木さんはひとりで作業します。
製作の流れは、コークスを燃料としたコンパクトな炉で、刃物の刃を支える土台となる地金と呼ばれる鉄を真っ赤に熱し、ひたすらたたきます。折り返してさらにたたきます。たたくことを鍛錬と呼びます。次に刃物の刃になる鋼を鍛え地金に接合します。冷やしたり形を整えたり、また熱して焼き入れしたり焼き戻したりして、荒おろしや研ぎ出しをして完成です。その間に銘打ちや柄付け(柄は藤巻・木・鹿角など自作の物)をします。
ステンレスを型抜きして研磨した刃物は作っておられませんので、一本一本製作に時間がかかります。刃物以外でも少量ではありますが、スプーンやフック、燭台なども製作されています。刃物にとって切っても切れないものに「研ぎ」がありますが、自分で研げるように鍛錬してあるそうです。
研ぎはまず、砥石の粒度(番数)800~1500番の粗めのダイヤモンド中砥石を使い、そのあと2000~4000番の細かい仕上砥石で仕上げる。コツは隙間を入れずに少量の水を垂らすことのようです。
船木さんの刃物は何処で購入できるかということですが、毎月の東寺弘法市と北野天満宮天神市に出店されています。
 北野天満宮天神市の店舗、北東の道路沿いにある。
北野天満宮天神市の店舗、北東の道路沿いにある。
船木さんはいつも研ぎをしている
船木さんはとても博識な方なので、客がいないときは研ぎ作業をしながら、刃物の歴史から研ぎ方などの実用的なことまで教えてくれます。世界的に有名なコペンハーゲンのレストラン「ノーマ(Noma)」のスタッフが弘法市を訪れて、テーブルナイフ採用の契約をしたそうです。また鷹峯のアマン京都から2Kmの道のりを歩いて、外国人宿泊客が工房をよく訪ねるそうです。
 上:アウトドア用文化包丁¥40000、下:刺身包丁¥21000
上:アウトドア用文化包丁¥40000、下:刺身包丁¥21000
 上下:アウトドア用ナイフ¥21000、中:テーブル用キッチンナイフ
上下:アウトドア用ナイフ¥21000、中:テーブル用キッチンナイフ
工房を訪ねる際はアポを取って訪れてください。昔京都ではどの町内にも1軒は鍛冶屋があり、京刃物は京土産の代表でしたが、今では4~5軒しか残っていません。
京小鍛冶 祥啓 鍛冶師:船木 祥啓
TEL:080-4480-2808(イベント開催時 8:00~16:00)
TEL:070-2823-0138(工房 10:00~17:00)
E-mail:hagane@hamono-s.com
HP: https:// hamono-s.com
工房の所在地
〒603-8491京都府京都市北区鷹峯仏谷4