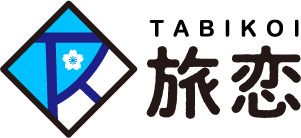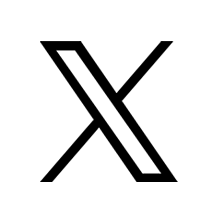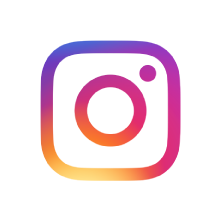楽園またはオアシスのような場所は、どこの都市にも必ずあります。
京都の最も眺望がすばらしく、リフレッシュできる場所は何処でしょうか?嵐山保津川沿いの道?円山公園?平安神宮岡崎界隈?京都御所?哲学の道?その場所は昔から決まっていました。
鴨川に架かる丸太町橋を数10m上がった鴨川西岸にある頼山陽の屋敷です。自ら「山紫水明処」と名付けたのに相応しく、眼前の鴨川越しに臨む東山がすばらしかったようです。まぁここが京都で一番だと言われても、頼山陽が決めたことなので、しかも江戸後期ですから説得力がありません。
鴨川の風景も昭和10年の水害以降は大きく変わりましたし、我々現代人はお気に入りの場所があると思います。そこで京都市上京区在住の私の楽園をご紹介します。そこは鴨川公園です。なんだ、やっぱり鴨川かよ⁈と思われますが、鴨川公園と言っても、北は上賀茂の柊野ダムから南は伏見の竹田橋あたりまで広大です。そこは、山紫水明処から1500m上流に行った今出川通の賀茂大橋から、出雲路橋までの右岸左岸で、その距離1Kmくらいです。
堤防は右岸が車道の賀茂街道で、葵祭のときの行列が上賀茂神社から北大路橋まで通ります。左岸は未舗装の遊歩道です。河川敷は右岸の方が広くて樹木が多く、クローバーの草原が広がっています。
狭い左岸の方は自転車道が整備されていてジョギングしている人も多いです。犬を連れた散歩の人、学生のトレーニング、橋の下で楽器演奏する人、読書する人、また賀茂川にも簡単に入れるので釣りをする人や犬を泳がす人など様々です
(地元民や学生が思い思いにくつろいでいる)
水質も昔と比べると見違えるほど良くなっています。昔は友禅染の染料を洗い流していたので、日によって水の色が違っていました。生活排水もうまく処理されていなかったようで、堰のところでは泡立っていました。それでも子供のころは賀茂川に入って魚を獲っていました。

 (鴨川デルタ全景。映画「パッチギ」の乱闘シーンのロケ地にもなった。
(鴨川デルタ全景。映画「パッチギ」の乱闘シーンのロケ地にもなった。
今やこんなにも外国人が集まってくる)
賀茂大橋で高野川と合流する鴨川デルタでは、昔は明らかに高野川の方が水はきれいでしたが、今では変わりません。ここには賀茂川と高野川をまたぐ飛び石がありすっかり有名になりました。驚くことに最近はこんな所にも外国人観光客が押し寄せています!ちなみに飛び石は渡るために設置されたのではなく、水の流れを緩め河床を安定させるのが本来の目的だそうです。余談ですが、鴨川デルタの東は京都大学学生の支配地、西は同志社大学学生の支配地などと言われています。
 (鯖街道の終着点は、秀吉が作ったお土居の出入り口があった。
(鯖街道の終着点は、秀吉が作ったお土居の出入り口があった。
京都家庭裁判所。葵橋の擬宝珠と葵の紋章の装飾)
すぐ上流にある出町橋は、若狭街道の出発点で、小浜から鯖など海産物を運搬したので別名鯖街道と呼ばれていました。一本上流に架かる葵橋のすぐ東には京都家庭裁判所があります。元々下鴨神社の糺の森が広がっていた場所です。都市に残る原生林糺の森の名の由来は、賀茂川と高野川の合流点なので「只洲(ただす)」という地名から来ているという説と、祭神の賀茂建角身命(タケツヌミノカミ)が民衆の争いを聞いて判定をしていた伝説があり、それが「糺す(ただす)の森」となり、裁判判定の発祥の地とも言われています。
四季の様子もお伝えします。
川沿いはほぼ桜並木なので花見の宴会は賑やかです。特に出雲路橋右岸と、葵橋から出町橋にかけた右岸はぎっしりです。中には土手の桜と桜の間で、横を車がビュンビュン通る場所で宴会を平気でやっている強者もいます。新入学生歓迎会も派手にやっています。BBQは禁止です。
夏は五山の送り火の大文字が、遮るものなく正面に望めます。点火の時間帯の賀茂街道は自動車通行止めになります。
秋は桜の葉が紅葉して彼岸花が咲きます。出町柳駅南の常林寺は境内のすべてが萩の花で覆われます。
(常林寺の門をくぐればすぐ萩の花が広がる。堤防の斜面には彼岸花、桜の葉の紅葉)
冬にはユリカモメが飛来し、比叡山の雪景色を背景にして群舞します。